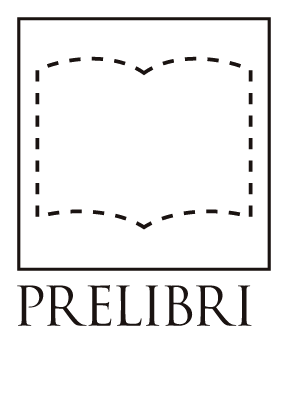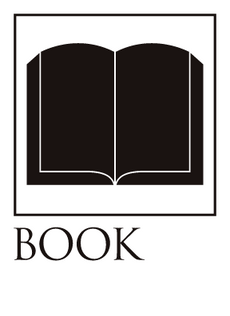編集手本 / 松岡正剛
Bibliographic Details
- Title
- Henshu Tehon / 編集手本
- Author
- Seigow Matsuoka / 松岡正剛
- Editor
- Osamu Kushida / 櫛田 理
- Designer
- Ryosuke Saiki / 佐伯亮介
- Director
- Osamu Kushida / 櫛田 理
- Images
- Photo by Bishin Jumonji 十文字美信、Atsushi Nakamichi 中道淳、Yuichi Sasaki 佐々木友一、Seiya Kawamoto 川本聖哉、Satoshi Nagare 永禮賢、 Editorial Engineering Laboratory 編集工学研究所
- Publisher
- EDITHON
- Year
- 2018
- Size
- 四六判(188mm×128mm)
- Pages
- 48
- Language
- Japanese / 日本語
- Binding
- Tehon-ori / 手本折
- Edition
- First edition / 初版
- Condition
- New / 新品
幾千の書物から万物を読み解く
伝説のエディター。
松岡正剛の編集指南書。
さまざまな道をゆく先人が「手本」としてきたことを肉筆で綴る「おてほん」シリーズ。その第一弾のために、松岡正剛が筆を執った。半世紀にわたり前人未到の編集世界を爆走してきた伝説のエディターが「ぼくが手本としてきたあれこれ」をこっそり教えてくれる、そんな仕立てになっている。松岡さんの傍でおよそ10年ほど編集見習いをしていた当方が企画・編集・発行した。
蛇腹のような製本は、このシリーズのために誂えたもの。「機械でつくる中世の本」を構想し、印刷会社と数ヶ月かけて共同開発した。大きな紙に切れ目を2本入れて折り畳むことで「継ぎ目のない蛇腹本」ができあがる設計になっている。「手本折(てほんおり)」と名づけた。
企画段階のわりと始めから「手書きの本」をつくることがイメージにあって、『葉隠』や『風姿花伝』、ダ・ヴィンチやパウル・クレーの手稿本がアタマにあった。だから、生生しい校正赤字もそのまま印刷し、懐からそっと出てきそうな造本にした。それは、現代の大量出版流通システムのなかで失われてしまった「本の香ばしさ」みたいなものに対するちょっとした挑戦でもあった。手稿本とはそうしたもので、手書きの本には、マジカルな読書が宿っている。それに、ぼくは、松岡さんの手書きが好きだった。
本書のオモテ面は、およそ3000字の書き下ろし原稿と本人による挿絵「戯画遊書(ギガユウショ)」で構成される。ウラ面は、十数本のアフォリズムとその脇にはさまざまな編集の舞台裏が垣間みえる写真が登場する。例えば、ワープロ専用機「書院」の前でいつも通り「千夜千冊」を執筆中のうしろ姿。例えば、照明家の藤本晴美さんとのリハーサルシーン。例えば、数寄屋造りの建築家・三浦史朗さんが設計した「井寸房(せいすんぼう)」で本を探しているところ、など。写真家は、十文字美信さんから当時のスタッフまで幅広く、松岡正剛事務所の協力で数千枚の写真アーカイブから厳選した。
この本ができたことを喜んでくれた、藤本晴美さん、三宅一生さん、ワダエミさんは、もういない。山本耀司さんは 「Yohji Yamamoto POUR HOMME」の春夏2021コレクションで、この本で初出した「松岡正剛のアフォリズム」を刺繍した 黒いジャケットを発表してくれた。すこしはマジックが効いただろうか。
※この本は、第53回造本装幀コンクール「日本印刷産業連合会会長賞」を受賞しました。
<編集後記>
師である松岡正剛は、2000年にはじめた「千夜千冊」を当時もいまも書きつづけている稀代の読書家として有名だけれど、それと同じくらいの熱量で「ノートする人」であることは、じつはあまり知られていない。
読書中も「本はノートのように汚すもの」と言って、本文をマーキングしたり、余白に赤ペンや青ペンで走り書きする。スタッフとの打ち合わせ中には、アタマに浮かんだ「図解」を白紙の上にスケッチする。パウル・クレーの『造形思考』のように、脳と目と手がワンストロークでつながっている人なのだ。だから、社内の打ち合わせやディレクションの場は、いつもたのしみだった。今日は、どんな造形的編集感覚があらわれるだろうか、と白紙の束と筆記具を準備して、ワクワクしながらそれが現れるのを待っていた。
ところで、夜な夜なうまれる「ノート」や「草稿」や「ドラフト」は、けっして印刷物になることはない。スタッフが保管するといっても、重要なドキュメントとして記録されるのはごくごく稀で、その場で生まれてはその場で消えていく、そういうものだった。
ある夜、20代〜30代の頃につけていたという「ノート」を見せてもらったことがある。スタッフのあいだでも、ほとんど知られていない秘密の手帖で、見せてほしいとお願いをしたら、書斎の奥から十数冊の古ぼけた大学ノートをひっぱり出して見せてくれた。
そこには、ページごとに「鉱物」や「機械」といったキーワードがページ上部に置かれていて、その見出しに沿って短い文章や引用文が手書きされていた。驚いたのは、そのヘッドラインが空白ページにも書かれていたことだった。ヘッドラインが先なのである。まるで道標のように、思考の飛石のように。それがメモランダムなノートではなくて、備忘録ですらない、と気づいた瞬間、なにかが氷解した。
松岡さんがノートしていたのは「情報の景色」だった。編集とは過去を向いてする仕事が多いけれど、既にあるものだけが編集者の領分ではない、という松岡さんの姿勢が、わたしをずっと支えてくれている。
Text by 櫛田 理