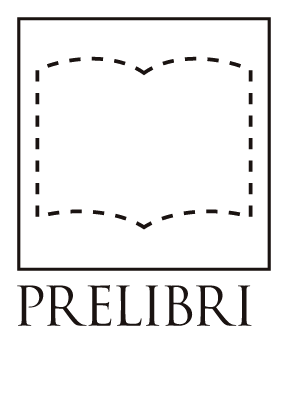MENUS
Bibliographic Details
- Title
- MENUS (Private Press)
- Author
- Anonymous / アノニマス
- Designer
- Anonymous / アノニマス
- Publisher
- Private Press / 私家本
- Year
- 1906-1911
- Size
- H240 × w145 × d50mm
- Weight
- 1000g
- Pages
- 212 pages
- Language
- French / フランス語
- Binding
- Relieur Binding / ルリユール製本
100年前の巴里で
夜な夜なひらかれた
晩餐会の献立。
1906年から1911年、元号にすると明治39年から明治44年にあたる6年間、公的機関が主催し、パリの官邸や大使館、高級ホテルなどで開かれた全212の饗応メニューを宴席ごとに1枚の紙にタイピングし、上製本に仕立てて残された記録です。メニューには年月日の他に主催者名や会場名まで記録されているものも多く、また、ワインリストについても漏らさず記載しており、後世、手にしたものにとっては、料理の歴史はもちろん、外交、或いは日本人の海外体験に関わる資料としてみることもできそうです。
扉には手書きで下記のような書き込みが認められます。
「西暦千九百0六年カラ同十一年に至ル/巴里滞在中ニ得タル宴席献立集/(大統領夜会・外務省、各国大使館被招宴)/参考の爲め小田君に●の贈す/昭和三十●年四月十九日」(/は改行、●は解読不能)
この書き込みから、フランスでの宴席に実際に招かれた日本人が残した記録とみられます。詳細については後述しますが、宴席の主催者や開催場所などから、当書の旧蔵者は単なる民間人ではなく、ある程度高位にあった公人だったのではないかとみられます。一体どういう人物だったのか - 最大のヒントが扉に書き込まれた一文に添えられている英文サインにあることは明白なのですが、そのサインが達筆すぎて解読できない。何度見ても分からない。分かれば俄然、面白さが増すだろう情報だけに、実に悔しい。このあたりに当稿執筆者の限界が…といったお話しはさておき。
肝心の、メニューに書き残された宴席の性格ですが、最も多いのがフランス共和国大統領主催の晩餐会や大統領官邸であるエリゼ宮での午餐会。その他、パリ日仏協会主催・一条宮殿下歓迎昼食会、フランス内務省晩餐会、アメリカ大使館主催晩餐会、ベルギー国王陛下晩餐会、フランス国立陸海軍学校・伏見宮殿下午餐会、アジアンミーティング月例昼食会など。その他、拾える単語を並べただけでも、フランスの農務省、産業省、海軍省、日本の梨本宮、小松宮、パリの高級ホテル、ル・ムーリス、ホテル・コンチネンタル、ホテル・マジェスティック・パリなど、きらびやかな固有名詞がひきもきらず、旧蔵者の在仏当時の立場を暗示します。
メニュー構成はというと、公的な宴席が多いこともあってか、ディナーの場合はコンソメや各種ポタージュなどスープに始まり、前菜(場合によって冷たいのと温かいの)、魚料理、シャーベットなど箸休め、肉料理、付け合わせ、プレ・デザート、デザート、食後のプチフールと続く”これぞフレンチ!” という堂々たるフルコースがほとんど。ランチの場合も現代感覚とは程遠い椀飯振舞で、結果、これ1冊で当時のフランス料理のメニュー名の宝庫となっています。
具体的にランチとディナーそれぞれ一例をあげると……
1906年10月31日のランチ - 牛の腎臓入りオムレツ、フィレステーキのりんご添え、鶏のロースト、フォアグラのパテ、サラダ、プラリネのアイス、フルーツ、デザート。これでランチのごく一般的な例です。一条宮殿下を迎えてのランチとなると、さらにオードブルと魚料理が加わり、ワイン(メドックとサンテミリオン)とシャンパーニュが用意されました。
旧蔵者帰国直前の1911年7月6日、送迎会と目されるホテルマジェスティックでのディナー -アミューズ、鶏かウミガメのスープ、米料理、白く仕立てた鶏のびっくり料理、アスパラガスのポーランド風、ソルベ、ポイヤック男爵の串焼き(!?)、リンゴのフォンダン、イギリス風グリンピース、ルーアンの高級鴨料理、ミカドサラダ、ナスのオーブン焼き、桃のアイス、プチフール、フルーツ。料理名のなかにつけ合わせが含まれているとしても10皿は超えます。ワインはシャトー・マルゴーの1893年など4種類。
興味深いのは、いまでは食材として扱われていない材料が使われていたり、料理名なのにあまりに詩的なせいか直訳してみたところで想像がつかないものが間々見受けられるところです。先に述べたディナーでいえば、「ウミガメのスープ」が前者の、「ポイヤック男爵の串焼き」などが後者の代表格で、こうなると想像力などで追いつくものでもなそさうです。ランチのボリュームもいまとは比べ物にならない重さで、それを食べる人間は姿かたちにそれほど大きな変化がないのに対して、食の文化と慣習とは、この1世紀の間だけでも、かなり大幅に変化していることが分かります。
渡航の交通手段が客船だった当時のこと、船が日本の港を発つと同時に乗客の食生活の欧化も始まっていたはずですが、しかし、このメニュー集に出てくる食材と料理、皿数をみるにつけ、船内とは比べるべくもないハードな食事だったことがうかがえます。日本での食生活と比べればその変化は激甚。試みに、この1冊から、旧蔵者氏が何日おきに宴席に招かれていたのかを算出すると、1906年3月から1911年7月まで約1735日の滞仏中に212回テーブルについたとして8日に1度という結果に。本格的なフランス料理をほぼ週に一度、しかも多くの場合フルコースで食べていたことになります。 米と味噌汁を日常食としていた日本人にとっては、さながら“お食べ地獄”だったのではなかろうかと、メニューのページを繰るこちらの胸とお腹が痛みます。
先のメニュー名のなかに「ミカドサラダ」なるものが出てきましたが、この他にもTokyoやSada-yacco、Fouji-Yamaといった日本語の名詞を織り交ぜたデザートや、ポタージュ・ジャポネーズなど、日本を思わせるメニュー名も散見されます。日本料理とは似て非なる料理だった可能性が高いものの、外国人にとっては日本を想像するための手がかりに、そして、日本人にとっては祖国の誇りを表し、もしかしたら、郷愁の念を少しばかり慰めたりするものだったのかも知れません。
Text by 佐藤真砂