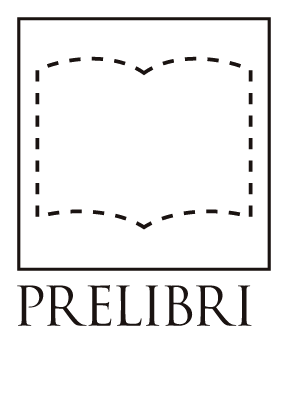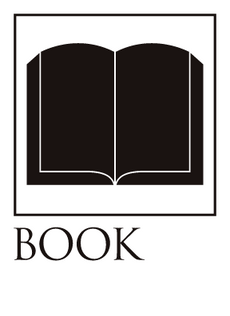書窓 vol.1-12
Bibliographic Details
- Title
- Shosou vol.1-12 / 書窓 vol.1-12
- Author
- 北原白秋、武井武雄、初山滋、村山知義、室生犀星、西村伊作、津田青楓、恩地孝四郎、岡本かの子、青柳瑞穂、村岡花子、庄司浅水、秋朱之介、斎藤茂吉、井伏鱒二、野島康三、他多数
- Editor
- Koshiro Onchi / 恩地孝四郎
- Designer
- Koshiro Onchi / 恩地孝四郎
- Director
- Publisher=Taro Shimo / 発行人=志茂太郎
- Publisher
- Aoi shobo / アオイ書房
- Year
- 1935-1936
- Size
- h227 / h232 × w157mm
- Weight
- 1: 1140g / 2: 1380g
- Pages
- 1: 454pages / 2: 608 pages
- Language
- Japanese / 日本語
- Binding
- vol.1-12 in 2 volumes / vol.1-12を2巻に合本した上製本
- Edition
- Limited numbered edition of 700 copies as a magazine / 雑誌としては700部の限定ナンバー付き
戦前の小さな雑誌出版。
美しい書物の周辺をかけめぐる
愛書家たちの夢のあと。
戦前のおよそ10年間にわたってアオイ書房が刊行した愛書誌「書窓」の創刊号(昭和10年4月10日発行)から12号までを合本した2冊。「書窓」の毎号の表紙は、恩地孝四郎による色刷り図案で、扉には限定番号(会員番号)を刻印。当時開発されたばかりの写植(写真植字)で本文を組版し、オフセット印刷した本文用紙には紙幣や証券にも使われる上質な局紙を用いた。毎号異なる趣向で、印刷研究特集、夢二追悼号、絵本特集、蔵票特集など、当時の書物愛好家たちが目を丸くしそうな特集を組んだ。連載コーナーでは、国内外の出版社のシンボルマークを紹介したり、会員が「この本を探してます」なんて情報を交換しあったり、手がけた本を装幀家自身が語る「自著自感」コラムがあったりと、いま読んでもそうとう面白い。
この「書窓」を手がけたのは、詩人で版画家で装幀家の恩地孝四郎で、恩地のエディターシップとアートディレクションがこの雑誌を普遍的な存在にしている。のちに、亀倉雄策の「クリエイション」(発行:リクルート)や赤塚不二夫の「月刊まんがNO.1」(発行:日本社)、最近では立花文穂の雑誌「球体」(発行:六耀社)など、デザイナーや漫画家が自ら編集長ないし責任編集として腕をふるった雑誌出版はあるけれど、装幀家やデザイナー自身が「本の雑誌」を編集したものは、ほとんど類例がない。
ところで、雑誌なのに700部限定だった「書窓」の出版人で、恩地と二人三脚でこの愛書誌を私信のように出し続けた志茂太郎(1900-1980)という人に、わたしは惹かれている。岡山県の酒造家、県会議員の長男として明治33年(1900年)に生まれ、1924年に北区王子に酒販店「伊勢元」を創業。1929年に中野区新井に伊勢元酒店を開店するのに転居した近所に、たまたま恩地孝四郎がいて意気投合した。1934年にアオイ書房を創業し、翌年35年には恩地孝四郎を編集者として「書窓」を創刊。創刊号のあとがき「雑用手帳」にこんな創刊の辞をのこしている。「『書窓』は読む雑誌であると同時に、眺めても楽しめる雑誌たらしめるべく、視的効果を高めるため、紙質印刷等には実に人知れぬ費用を投じておるのであります。(中略)アオイ書房は純粋に私の道楽仕事です。本を作って儲けようなどとは、私はかつて一度も考えて見たこともありません。」志茂太郎のような出版人はもういない。好きな出版に投じられる財力はうらやましい限りだが、それ以上に活字と書物をこよなく愛していた。版元の経営者でありながら、文字の組版はもとより、執筆・編集・校正・渉外・通信販売の一切をやっていたのが、志茂太郎というひとだった。たんなる道楽者であろうはずがない。
志茂太郎は、命がけで美しい本を守ろうともした。太平洋戦争の末期、いよいよ戦況があやしくなり、政府は「変体活字廃棄運動」というもっともらしい名前をつけた国策を実行した。実態は、明朝体以外のあらゆる書体の活字を”変体活字”と称して、この”不要な”活字鉛を溶かして兵器に使ってしまおうというのだった。これに激昂した志茂は、激烈な抗議文を「書窓62号」に掲載した。政府の暗躍を「許されざる極悪非道の暴挙」と罵り、出版界の決起をうながした。このあたりの事情と顛末は、片塩二朗『活字に憑かれた男たち』(朗文堂)に詳しい。この檄文は当時の出版・印刷界におおきな衝撃をあたえたが、危険人物として官憲に目をつけられ、昼夜つきまとわれて、ついにアオイ書房は廃業。生業である伊勢元も閉店し、郷里である岡山県の山の城へ引き上げざるをえなくなった。以降、二度とふたたび上京することはなかったという。その後、郷里で刊行した「愛書会通信」は戦後の蔵書票愛好家たちに引き継がれ「日本書票協会通信」として現在も刊行している。志茂は書票という小さな本の世界に遁世し、そのまま岡山で没した。この志茂太郎なくして「書窓」もアオイ書房が発行した恩地孝四郎のうつくしい書物の数々も生まれなかった。
最後に、創刊号の巻頭に寄せられた北原白秋の詩文がとてもよいので、少し長いが原文をそのまま掲載する。最後の三行は、なんどでも反芻したい。
雪と螢 ー「書窓」に寄す
北原白秋
そのむかし、わたしたちの書を読んだ窓には
(ああ、何とクラシックな)
あの螢のにほひがした、
雪のあかりもさした。
わたしは久留米絣の筒袖を着て、
朗々と読んだ、少年のきばった声で。
さうだ、さうだ、
ほやのくすんだランプも
紙の障子もなつかしかった、
何でも読むものがおもしろくて、
何でもよく暗記したものだ。
あ、それでも
たったひとつわからない何かがあった、
何かが。
今、ちやうど、うちの子があの歳になる、
ちやうど、この父のあの頃のやうに
朗々と読んでゐる、きばった声で。
何でも読むことがおもしろさうで、
すっかり大人になったつもりでゐる、
なるほど聡しいものだ、とは思ふが、
それでもちっともわかってはゐないのだ、
あの一つの秘密だけは。
かはいい奴、
わからぬことはわからずとよい、
今にわかって驚くのだ。
この父がさうだったが、考へて見ると
あの頃にわからなかったことはわかったやうでも、
わかったやうに思へたものは却って
わからなくなって了った。
この子はと思ふ、
この子も中学の一年にはなったが、
なんとまだ幼いことだ、
何でもわかったやうな顔をして、
その実、まるっきり子供なのだ。
電燈があまりに明るいのだ、
窓があまりに透明な硝子なのだ、
外からあまりに見え過ぎるのだ。
※「書窓」は103号の時点で、1944年6月に休刊。
Text by 櫛田 理